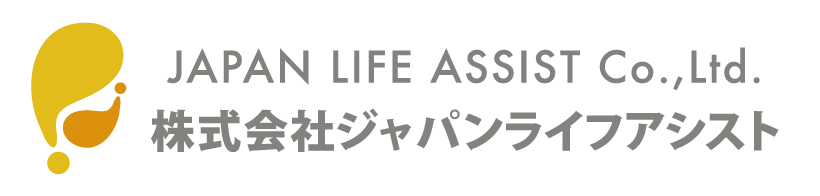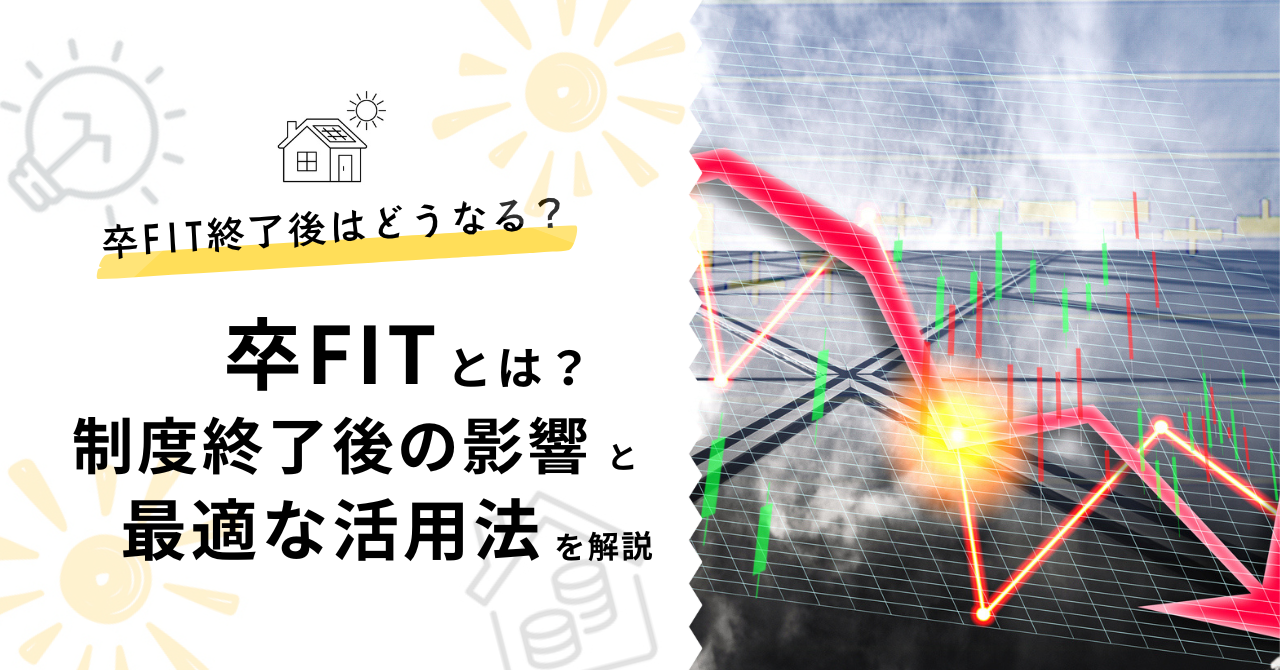卒FITとは?制度終了後の影響と最適な活用法を徹底解説
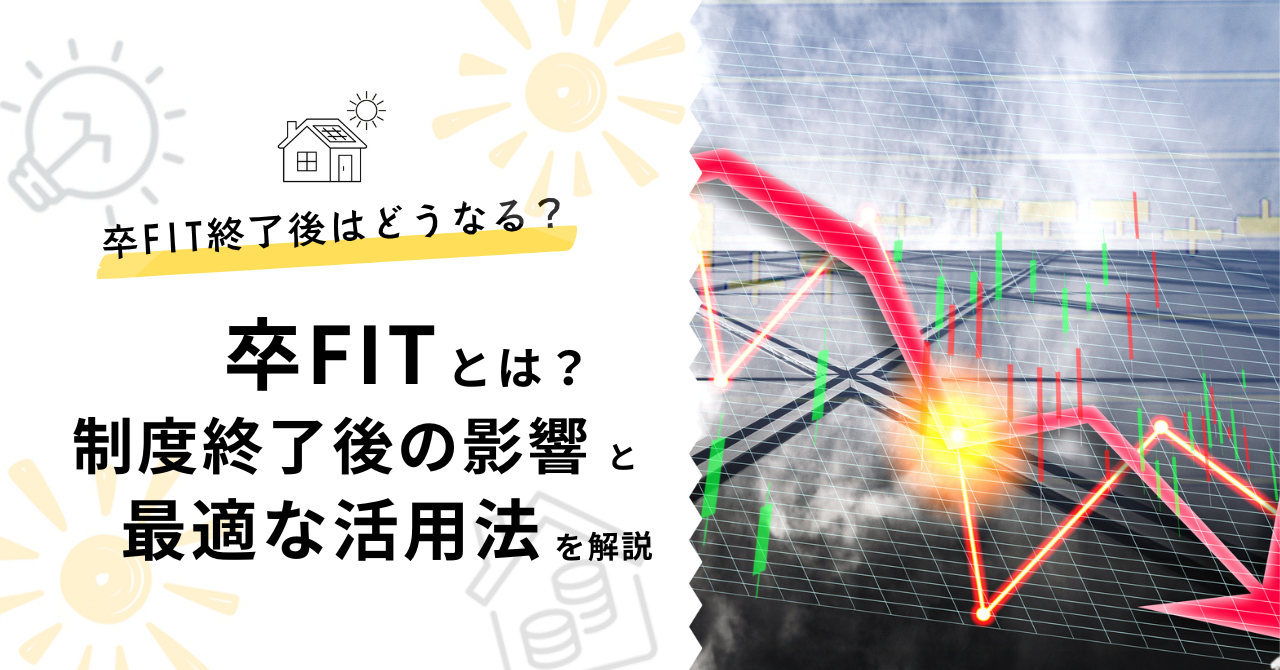
太陽光発電を導入してから10年が経過し、そろそろ「卒FIT」という言葉が気になっている方も多いのではないでしょうか。
卒FITとは一体何なのか、そして卒FIT制度終了後にどのような影響があるのかを知ることは、これからのエネルギー生活を考えるうえで非常に重要です。
このコラムでは、卒FIT制度の基礎知識から、制度終了後の最適な活用法などを詳しく解説しますので、自分のライフスタイルに合った最適な選択を見つけましょう。
卒FIT制度とは?知っておきたい基礎知識
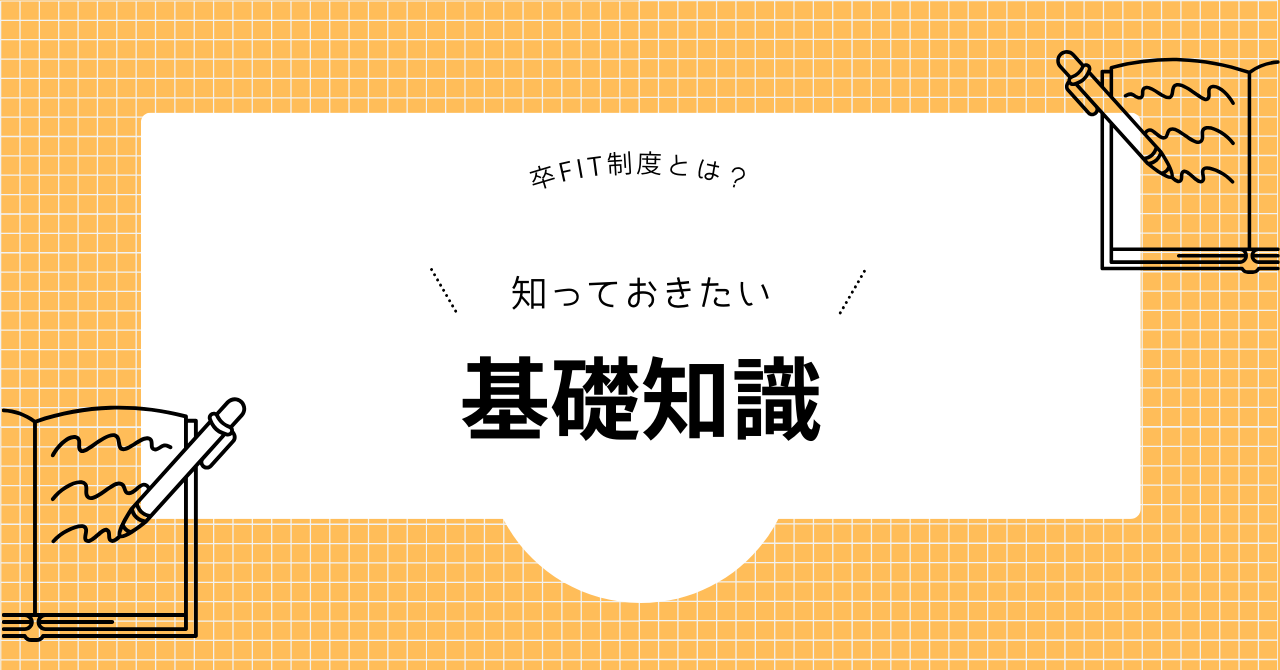
「FIT制度」は、太陽光発電を含む再生可能エネルギーによって発電された電力を一定期間、固定価格で買い取るという仕組みです。ここでは、FIT制度の仕組みや目的を詳しく解説します。
FIT制度とは?その仕組みと目的
FIT制度とは、日本語で「固定価格買取制度」といいます。
再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が保証する制度です。地球環境にやさしい太陽光や風力などの再生可能エネルギーの普及拡大することを目的としてつくられました。
なお、太陽光発電の場合は、設置した太陽光発電システムで発電した電力を高い価格で買い取ってもらえるため、初期投資の回収がしやすくなっています。
しかし、この買取り制度は永続的ではなく、期間が終了すると買い取り価格が大幅に下がってしまいます。
卒FITとは何か?対象者とタイミング
「卒FIT」とは、FIT制度の固定価格買取の適用期間が満了することを指します。
太陽光発電システムでは設置してから10年が経過した場合に卒FITを迎えます。対象者は、2009年以降に太陽光発電を導入し、FIT制度を利用してきた家庭が中心です。
卒FITを迎えた場合、1kWhあたりの買取価格が半額以下となることも珍しくありません。
例えば、2012年の買取価格は、1kWhあたり約40円以上でしたが、2025年には15円まで下がっています。
これまでの価格で売電ができなくなるため、余剰電力の新たな活用法を検討する必要があります。
経済産業省のデータによると、2023年には累計で約165万件が卒FITを迎えており、今後も増えていく予想です。
※参考:経済産業省資源エネルギー庁「住宅用太陽光発電設備の FIT買取期間終了に向けた対応」
卒FIT後の買取価格の変化と影響
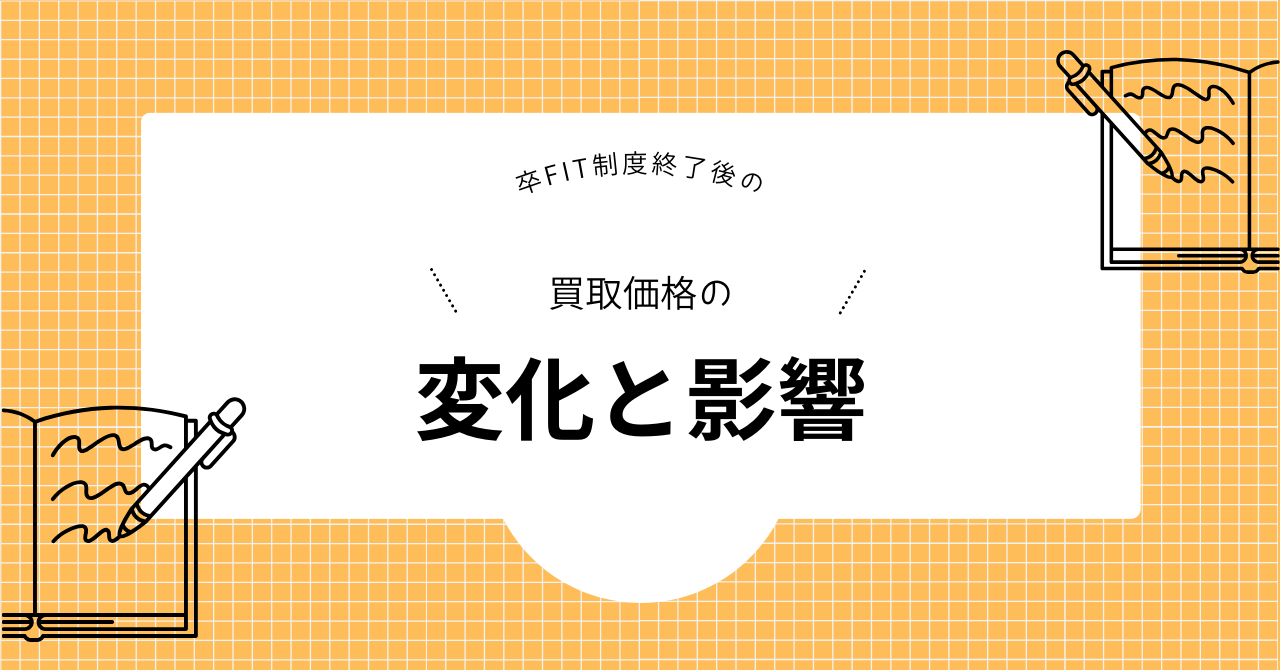
卒FIT後の買取価格の下落は避けられませんが、どの程度の影響があるのか、具体的な数字を見てみましょう。また、売電を継続する場合の注意点や、高値買取を目指す方法についても解説します。
買取価格の下落と収入への影響
経済産業省によると、2025年現在の再生可能エネルギーの買取価格は1kWhあたり約8~15円程度となっています。
例えば、FIT期間中は1kWh40円で年間約12万円(3,000kWh/年)の売電収入があったとします。しかし、卒FITで売電価格が1kWh8円になってしまった場合、年間の売電収入は2万4,000円程度で、年間約10万円もの収入減となってしまいます。
実際の売電価格の下落率は電力会社との契約など、ご家庭によりますが、この例のように電気料金の節約率が下がってしまう可能性が高いです。
※参考:買取価格・期間等|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー
売電を継続する場合の注意点
卒FIT後も新しい買取価格で売電を継続することは可能ですが、自動で売電を続けられる契約の場合と、卒FITのタイミングで自動継続されない契約形態があるため、電力会社との契約内容を確認する必要があります。
継続されず売電されなかった余剰電力は、一般送配電事業者に無償で引き受けてもらうことになるため、卒FITを迎える前に契約内容を確認しておきましょう。
卒FIT後におすすめの電力活用法
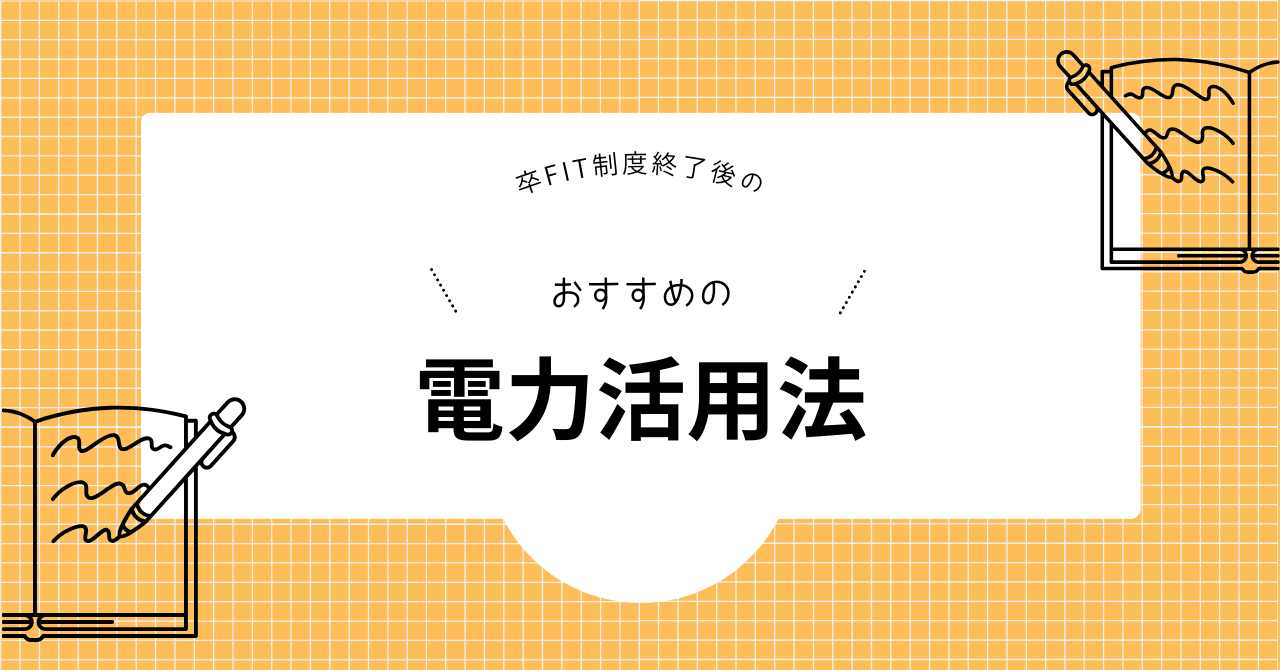
余剰電力は、売電以外にも有効活用する方法があります。ここでは、卒FIT後におすすめの電力の活用法について解説します。
蓄電池導入で自家消費率を高める
蓄電池を導入して自家消費率を高める方法は、卒FIT後の電力活用としておすすめの選択肢です。
蓄電池を導入すると日中に発電した電力を蓄えられるため、夜間や天候不良時に使用することができるようになり、買電量を減らすことができます。
また、停電が起きた際にも蓄えた電力を活用できるため、災害時の対策としても有効です。
蓄電池の導入には、容量5~12kWh前後で、約100~200万円程度の費用がかかりますが、国や自治体の補助金制度を活用できるため、費用負担は軽減することができます。
エコキュートや電気自動車(EV)を活用する
卒FIT後の余剰電力を有効活用する方法として、エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯機)や電気自動車(EV)の充電に使う方法も効果的です。これにより、売電価格が低下した電力を自宅で最大限活用し、買電電気代を削減できます。
エコキュートは、夜間電力を利用してお湯を沸かす仕組みですが、昼間の太陽光発電の余剰電力を利用するため、ガスより経済的にお湯を沸かすことができます。
また、電気自動車を所有している場合、余剰電力を車のバッテリーに活用することもできます。V2H(※1)システムを導入することで、双方向で電力をやり取りすることも可能です。これにより、再生可能エネルギーをさらに有効活用することができるようになります。
※1)V2H(Vehicle to Home)とは、電気自動車と太陽光発電が取り付けられた家の双方向で電力をやり取りできるようになる機器。
電力会社との新たな契約プランを検討する
電力会社が提供する新たな契約プランを検討する手もあります。
例えば、時間帯別の電気料金プランを利用し、割安な時間帯に電力を購入することで光熱費を節約できます。
また、一部の電力会社では卒FIT後の太陽光発電ユーザー向けの特別プランを提供しています。これらのプランでは、電気の買い取りや売電価格の優遇が受けられる場合があります。
売電先を切り替えて高く売る
もし売電を継続するなら、売電先をより高い価格で買い取ってくれる新電力会社系へ切り替えるのも手です。
新電力会社は電力自由化に伴い生まれた会社のことで、従来の大手電力会社よりも売電価格が高いことがあります。
例えば、一部の新電力会社では、1kWhあたり約10円以上で買い取ってくれる場合もあります。従来の電力会社よりも高い価格設定のため、売電収入の減少を抑えることが可能です。
蓄電池導入のメリットとデメリット

蓄電池の導入にはメリットとデメリットがあります。ここからは蓄電池の導入を検討中の方に向け、蓄電池のメリット・デメリットを詳しく解説します。
蓄電池導入のメリット
蓄電池を導入することで、電力の自家消費を最大化し、エネルギーの有効活用が可能になります。
- 買電電気代の節約ができる
- 非常用電源として活用できる
- 環境にやさしいエネルギーを使える
蓄電池は、昼間に蓄えた電力を夜間に使うことで、電力会社からの買電量を減らし、買電電気代を節約できるのが大きなメリットです。
電気料金プランによっては、深夜の安価な電力をため、昼間に活用するという方法も選択できるようになります。蓄えた電力は停電時に使うこともできるため、非常用電源としての利点も高いといえるでしょう。
また、太陽光発電はCO2排出量が少ない再生可能エネルギーとされています。蓄電池の導入で、さらに環境に配慮した暮らしを実現することが可能です。
蓄電池導入のデメリット
一方で、蓄電池の導入にはいくつかのデメリットもあります。
- 初期費用が高い
- 寿命が10~15年
- 設置スペースの確保が必要
蓄電池の導入には、本体費用や設置工事費を含めて約100万円以上かかることが一般的です。補助金制度を活用すれば負担を軽減できますが、それでも高額な投資となる点はデメリットになりえます。
また、蓄電池には寿命があり、一般的に10〜15年程度といわれています。使用回数が増えると蓄電容量が徐々に低下するため、長期間の運用を考える場合は、保証内容や交換コストも認識したうえで計画立てることが重要になります。
加えて、蓄電池の設置スペースを確保しなければならないという点も留意が必要です。蓄電池には屋内・屋外のタイプがありますが、設置環境によっては追加の工事が必要になる可能性があります。
初期費用を軽減する補助金の活用
蓄電池の導入には初期費用が高いというデメリットがありますが、国や自治体の補助金制度を活用することで負担を軽減できます。
国の補助金制度の例は、以下があげられます。
| 2024年までの補助金例 | 補助金額 |
| 子育てエコホーム支援事業 | 64,000円/戸 |
| DR補助金 | 1kWhにつき3.7万円(上限額60万円) |
なお、補助金の利用には製品や性能などに条件があるため、事前に確認が必要です。
ジャパンライフアシストでは、補助金の申請代行とサポートをしているため、蓄電池の導入をご検討している方は、お気軽にお問合せください!
※参考:エコ住宅設備の設置【リフォーム】|子育てエコホーム支援事業【公式】
※参考:令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
卒FIT後に最適な選択をするためのポイント

卒FIT後の余剰電力の活用法がどれが最適かは、各家庭の状況によって異なります。ここでは、卒FIT後の活用法で最適な選択をするためのポイントを解説します。
自家消費と売電|どちらが得かを比較しよう
自家消費と売電のどちらが経済的に有利かは、現在の発電状況などを考慮して判断する必要があります。特に、卒FIT後は売電単価が下がるため、慎重なシミュレーションが重要です。検討の際は、次の項目を確認しましょう。
- 現在の電気料金と売電価格の差
- 電力消費量と発電量のバランス
- 蓄電池の導入効果
例えば、買電料金が1kWhあたり30円、売電価格が8円の場合、発電した電力を自家消費すれば1kWhあたり22円の節約になります。一方、売電すれば8円の収入にしかならないため、基本的には自家消費のほうが経済的メリットが大きいと考えられます。
ただし、余剰電力が多く自家消費しきれない場合は、売電を組み合わせることで収益の最大化が可能です。
また、蓄電池の導入で自家消費率を高めるとよりお得になりますが、初期投資がかかるため、費用の回収期間を加味して判断する必要があります。
どちらが得かを判断するためには、年間の電気使用量と太陽光発電の発電量を把握し、具体的な収支シミュレーションをおこないましょう。
ライフスタイルから活用法を選ぼう
家庭ごとのライフスタイルから、電力の使い方を考えるのもひとつの手です。
例えば、日中家に人がいる場合は自家消費のメリットが高くなり、逆に夜間の消費が多い家庭は蓄電池の導入をすると昼間に発電した電力を活用できるというケースがあります。
また、地球環境への配慮を特に意識する方は、環境負荷を減らす観点から自家消費を選ぶのもよいでしょう。このように自分たちのライフスタイルから活用法を選ぶ視点も重要です。
専門家への相談と最新情報を収集をしよう
卒FIT後の選択肢は多岐にわたるため、専門家への相談もおすすめします。プロに相談することで、収支シミュレーションなども含め、的確なアドバイスが得られます。
また、インターネットで太陽光発電・蓄電池などの最新情報の収集もおこないましょう。例えば経済産業省や各自治体のホームページでは、補助金制度の情報が年度ごとに更新されています。
ジャパンライフアシストでは、お客様に補助金のご提案から、代行申請もしていますので、まずはお気軽にお問合せください!
まとめ
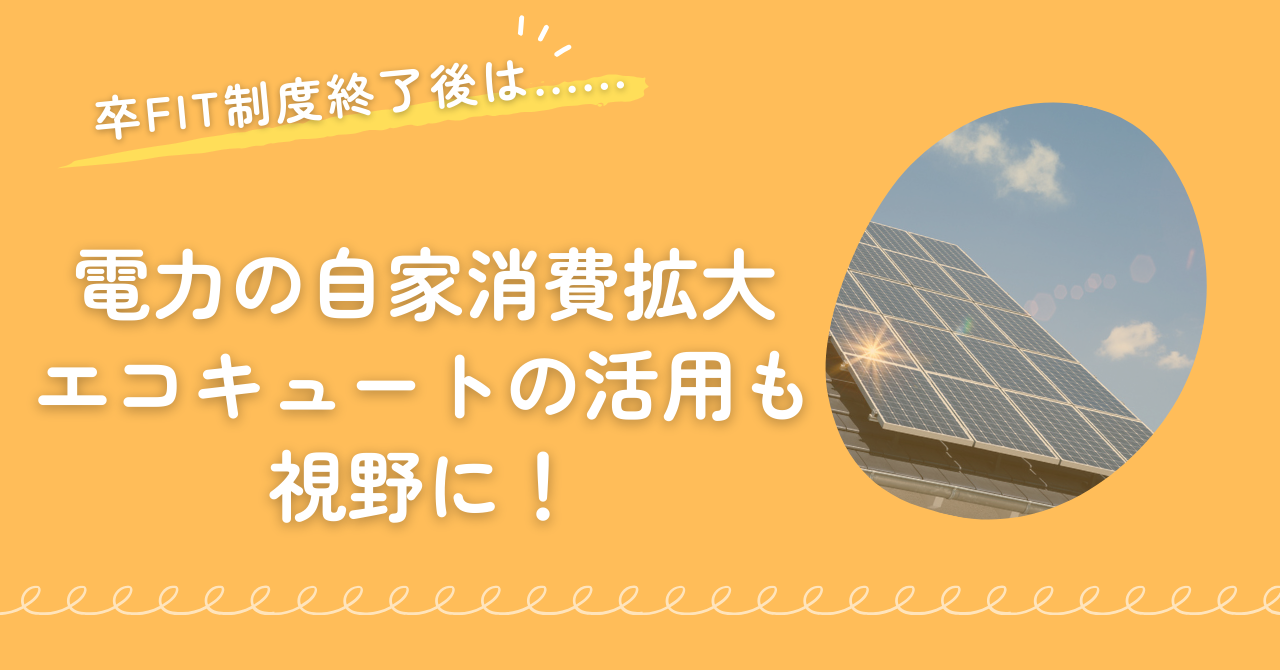
卒FITを迎えるにあたり、売電価格の下落や余剰電力の活用方法について理解することが重要です。
余剰電力は自家消費の拡大やエコキュートやEVへの活用、新たな売電先の検討など、さまざまな選択肢があります。
自分のライフスタイルや経済状況に合わせ、最適な方法を選びましょう。専門家への相談や最新情報の収集も忘れずにおこない、賢くエネルギーを活用しこれからの生活をより豊かなものにしていってください。
蓄電池の導入など卒FIT後の対応を検討している方は、ぜひジャパンライフアシストにご相談ください!まずは資料請求・お見積もりから!