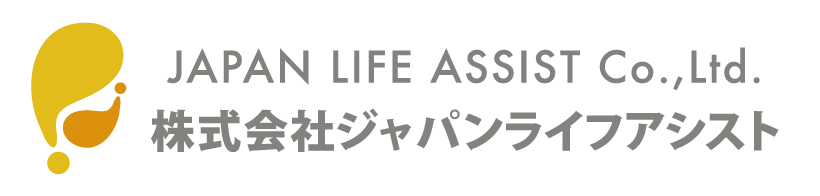卒FIT後の賢い選択|自家消費への切り替え方法とメリット

太陽光発電を導入された皆さまは、FIT制度の終了、いわゆる「卒FIT」に直面する時期が近づいているかもしれません。卒FIT後、どのように太陽光発電を活用すべきかお悩みではありませんか。
このコラムでは、卒FIT後の最適な選択肢である自家消費への切り替え方法と、自家消費に切り替えることのメリットについて詳しく解説します。
卒FIT後の対応策と選択肢

卒FIT後には、大きく分けて3つの選択肢があります。それぞれの特徴と条件を理解し、自分に最適な方法を選びましょう。
売電を継続する方法
まず卒FIT後も売電を続ける選択肢もあります。多くの電力会社では卒FIT向けの新たな買取プランを提供しています。ただし、買取価格は、FIT期間中よりも低く設定されていることが一般的です。
もし継続して売電をおこなうためには、電力会社との新たな契約が必要です。契約条件や買取価格は各社で異なるため、複数の電力会社を比較検討するようにしましょう。
また、売電収入が減少する可能性が高いため、収益性の見直しも必要です。一部の地域やプランでは、特定の条件下で高い買取価格を提示している場合もあります。最新の情報を収集し、最適な契約を選択しましょう。
自家消費へ切り替える
売電から自家消費へ切り替えることは、卒FIT後の有力な選択肢です。自家消費とは、発電した電気を自宅で直接使用することを指します。
自家消費に切り替えることで、電気代の削減や電力の自給自足が可能になります。特に電気料金が高騰している現在、自家消費のメリットは大きいといえるでしょう。
なお、切り替えには、蓄電池の導入や設備の調整が必要となる場合があります。しかし、初期投資を助ける補助金制度も存在するため、経済的な負担は軽減できる可能性が高いです。
自家消費の拡大は環境への貢献度も高まるため、持続可能な社会に寄与することにもつながります。
太陽光発電システムの撤去・廃止
最終的な手段として、太陽光発電システムの撤去や廃止を検討する方もいます。考えられる理由としては、設備の老朽化や維持費用が嵩むケースなどです。
撤去費用がかかりますが、土地や屋根のスペースを新たな目的で活用できるといったメリットもあります。ただし、一度撤去すると再設置には大きなコストが発生する点は留意が必要です。
また、環境負荷の観点からも、撤去よりも活用方法を見直してみることがおすすめです。決断する前に一度は専門家に相談し、全ての選択肢を検討してみましょう。
なぜ卒FIT後は自家消費に切り替えるべきなのか

自家消費への切り替えが推奨される理由は、多岐にわたります。ここでは、その主な理由と発電した電気をご家庭で使用するメリットについて詳しく解説します。
売電価格の低下で収益性が低くなるため
卒FIT後、売電価格は大幅に低下します。これにより売電による収益性が大きく減少することが予想されるでしょう。
具体的には、これまでの買取価格の半分以下になるケースもあります。売電収入に依存していた場合、家計への影響は避けられません。
しかし、自家消費に切り替えることで、発電した電気を無駄なく活用することが可能です。売電よりも高い節約効果が期待でき、経済的なメリットが大きくなることが期待されます。
電気代削減による家計へのメリット
自家消費は、電気代の大幅な削減につながります。発電した電気を自宅で使用することで、電力会社から電気を買うこと=買電量を減らせるためです。
総務省のデータによると、家庭の電気代は2021年以降は上昇傾向が続いています。自家消費により、この負担を軽減できるのは大きなメリットです。
冷暖房や家電製品の多様化により、電力消費が増える中、自家消費は強い味方となります。
環境への配慮とエネルギー自給率の向上
自家消費は、環境への配慮にもつながります。再生可能エネルギーを積極的に使用することでCO2排出量が多い燃料エネルギーの消費が減るため、結果的にCO2排出量を削減できます。
また、エネルギー自給率の向上にも寄与することにもつながるため、海外からのエネルギー資源に依存する日本の現状を改善する一助にもなるでしょう。
卒FIT後の自家消費型へ切り替える手続きとポイント

自家消費への切り替えは、多少煩雑な準備が必要です。ここでは必要になる手続きなどのポイントをわかりやすく紹介します。
自家消費型への切り替えに必要な手続き
卒FIT後に自家消費型へ切り替えるには、電力会社や設備の設定変更など、いくつかの手続きが必要です。主に必要な手続きは以下のとおりです。
- 売電契約の見直し
- 蓄電池などの検討
- 設備設定の変更
- 補助金の申請
まず電力会社との売電契約の見直しが必要です。
制度が終わる数か月前に買取期間満了通知が届くので、売電を停止するか、余剰分のみ売電するかを決定します。この際、もし契約を継続するとしても、自動更新ではない場合もあるので注意してください。
次に自家消費を最大化するために、蓄電池などの設置をおこないます。設置をしたら専門業者に依頼し、パワーコンディショナーの設定を自家消費向けに変更することも必要です。
また、蓄電池などの導入で補助金を活用したい場合、本体購入や工事の前に手続きが必要です。適用条件もあるので、早い段階で自治体のホームページや窓口で確認をおこないましょう。
設備の見直しと導入する機器
自家消費を最大化するためには、設備を見直し、自家消費を高められる機器の導入が必要です。自家消費を拡大したい場合、次の設備の検討が必要になります。
- 蓄電池
- HEMS
- エコキュート
蓄電池
蓄電池は、電力を蓄えて必要なときに使用できるようにする装置です。太陽光発電で発電した電力をためて、夜間や停電時に活用できるようになります。例えば電気代が高い時間帯に蓄電池に蓄えた電力で賄えれば、電気代の節約になります。
HEMS(Home Energy Management System)
HEMSは、エネルギーの使用状況を見える化し、電力管理を助けてくれる設備です。必須な設備ではありませんが、より効率的な電力管理をしたい場合に選択肢になります。
例えばオール電化や電気自動車を使用しているなど電力消費が多いご家庭に向いています。
エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯機)
一方、エコキュートは、大気中の熱を利用して効率的にお湯を沸かすヒートポンプ式の給湯システムです。
電気を使って少ないエネルギーでお湯を作るため、従来の電気温水器に比べて電気代を大幅に削減できます。
太陽光発電と組み合わせることで昼間の余剰電力を活用し、経済的な運用が可能です。
専門家へ相談
自家消費への切り替えは、ご家庭の電力消費量や余剰電力に合わせ、プランや蓄電池の策定をおこなう必要があるため、信頼できる専門家によるサポートが必須です。
この際に依頼する「専門家」は、住宅用太陽光発電の施工や保守などをおこなう施工会社・業者になります。これらの業者では余剰電力に合わせた最適な設備の提案や、補助金申請のサポートをおこなってくれます。
また、業者を選ぶ際には、導入後のメンテナンスやアフターサービスにも注目しましょう。契約前に複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが大切です。信頼性や実績、口コミなどもしっかりと確認してください。
長期的な視野でサポートしてくれるパートナーを選ぶことで、安心して自家消費を始めることができます。
ジャパンライフアシストでは、補助金の申請代行もおこなっているため、蓄電池の導入を検討している方はお気軽にお問合せください!
自家消費型への切り替えに必要な設備費用

自家消費を効果的におこなうためには、適切な設備の導入が重要です。ここでは、自家消費に必要な設備と費用について解説します。
蓄電池の導入費用
蓄電池の導入費用はメーカーや容量によりますが、70万円~260万円程度が相場価格です。なお、容量の目安と費用相場は以下のようになっています。
| 蓄電容量(kWh) | 相場 |
| 5kWh未満(小規模家庭向け) | 約70万〜100万円 |
| 5kWh〜10kWh(一般家庭向け) | 約100万〜150万円 |
| 10kWh以上(大容量・ZEH住宅向け) | 約185万〜260万円 |
※2025年2月調べ
蓄電池は安くありませんが、補助金制度を活用できる場合が多いため、導入費用を軽減できる可能性があります。補助金については、後述の補助金の活用をご確認ください。
エコキュートやHEMSの導入費用
エコキュートやHEMSの設備の導入費用の相場は、以下のとおりです。
| 費用相場 | |
| エコキュート | 約30万〜80万円 |
| HEMS | 約15万〜20万円 |
補助金の活用で費用を抑えよう
設備導入の初期費用を抑えるために、国や自治体の補助金を活用しましょう。
本年分はまだ発表はありませんが、再生可能エネルギーの普及を促進するため、例年に引き続き以下の制度などが拡充されることが予想されています。(2025年2月調べ)
| 2024年までの補助金例 | 補助金額 |
| 国:子育てエコホーム支援事業 | 64,000円/戸 |
| 国:DR補助金 | 1kWhにつき3.7万円(上限額60万円) |
| 東京都:災害にも強く健康にも資する 断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 「蓄電容量6.34kWh未満」 1kWhあたり19万円(上限95万円) |
| 「蓄電容量6.34kWh以上」 1kWhあたり15万円(100kWh未満) ※補助率:設置費用の3/4が上限 |
なお、補助金の対象となるには、蓄電池の製品などに条件があるため、蓄電池の購入を決める前にご確認ください。
※参考:エコ住宅設備の設置【リフォーム】|子育てエコホーム支援事業【公式】
※参考:令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
※参考:環境局「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」
補助金の金額や条件は地域によって異なります。最新の情報を自治体のホームページや窓口で確認してください。
申請には期限や必要書類があるため、早めの準備が肝心です。補助金を上手に活用して初期投資を抑え、早期の投資回収を目指しましょう。
ジャパンライフアシストでは、適用される補助金のご説明から、補助金の申請代行もしていますので、まずはお気軽にお問合せください!
自家消費を最大化するためのポイント・注意点

自家消費を効果的におこなうためには、日々の工夫と適切なメンテナンスが重要です。ここでは、そのポイントと注意点を紹介します。
効率的な電力利用と節電対策
電力の使用時間帯を意識し、発電した電気を最大限活用しましょう。
具体的には昼間の太陽光発電時に家電を使用すると効果的です。タイマー機能を活用し、洗濯機や食器洗い機を昼間に運転するなどの工夫をするとよいでしょう。
また、高効率の家電製品に買い替えることも、電力消費を抑える一助となります。家族全員で節電意識を高め、小さな積み重ねを大切にしましょう。
設備メンテナンスと長期的な運用方法
太陽光パネルや蓄電池の定期的なメンテナンスは欠かせません。手入れをすることで性能を維持し長期的な運用を可能にします。
ただし、必ず点検や清掃は専門業者に依頼しましょう。床や地面に設置された機器周りの掃き掃除程度はよいですが、機器に触れる必要がある範囲は安全面の観点からも個人でおこなわないでください。
また、もし異常が見られた場合は早急に対応することが重要です。いざという時のためにもメーカーの保証期間やアフターサービス内容も確認しておくと安心です。
将来のエネルギー事情と動向を見据えて
エネルギー政策や技術の進歩は日々進んでいます。将来の変化に備え、最新の情報を収集しておくことも大事です。近年は電力の自由化や再生可能エネルギーの推進により、新たなサービスや技術が登場しています。
また、必要に応じて設備のアップデートや新サービスの導入を検討することも重要です。将来を見据えた柔軟な対応が、長期的なメリットにつながります。
まとめ

卒FIT後の対応策として、自家消費への切り替えは多くのメリットがあります。自家消費率が高まれば、経済的な負担を軽減し環境にも配慮した暮らしを実現できます。
自家消費へ切り替える際は、専門家のサポートを受けつつ適切な設備を選定して自家消費を最大化しましょう。将来を見据えた賢いエネルギー活用で、より豊かな生活を手に入れてください。
蓄電池の導入など卒FIT後の対応でお悩みの方は、ぜひジャパンライフアシストにご相談ください!まずは資料請求から!