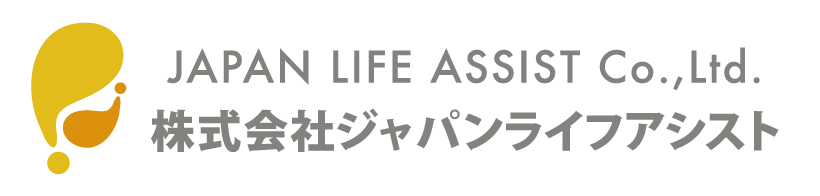家庭用蓄電池のデメリットとは?後悔しないための選び方と注意点

近年、環境意識の高まりや電気料金の節約、そして災害に備える手段として「家庭用蓄電池」の導入が注目を集めています。
しかし、蓄電池は高額な投資であり、デメリットを理解せずに導入すると、期待していた結果が得られず後悔してしまう可能性があります。
そこで、このコラムでは、家庭用蓄電池を導入する前に知っておきたいデメリットや、後悔しない蓄電池の選び方、よくある質問について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
家庭用蓄電池のデメリット
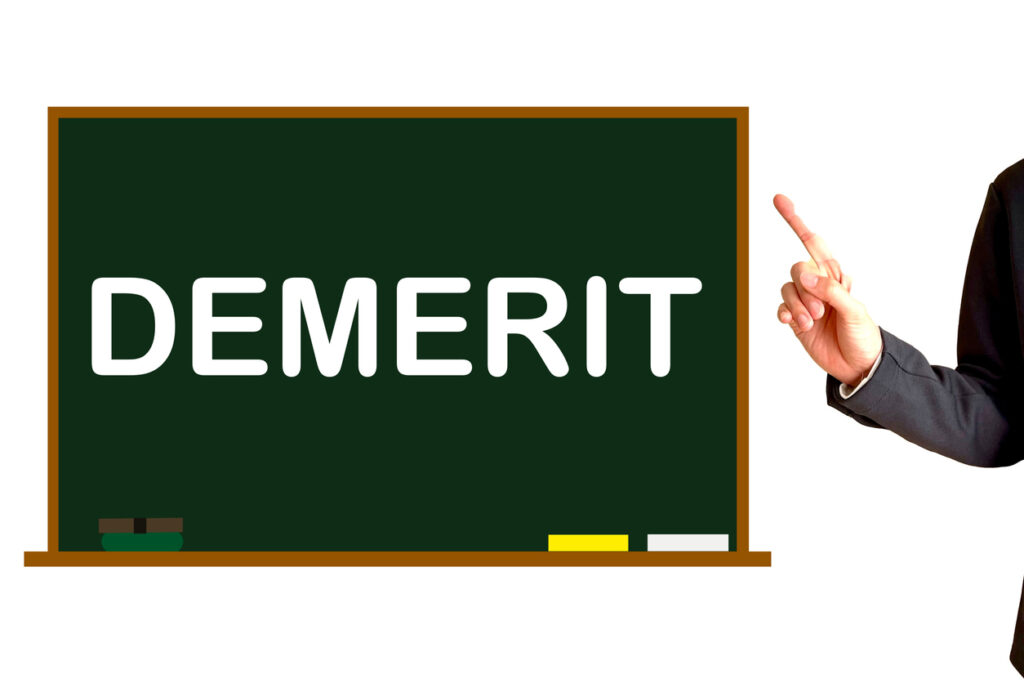
蓄電池は余剰電力の活用方法が増えるなど多くのメリットがある一方、デメリットも存在します。蓄電池の導入前にデメリットを確認しましょう。
初期費用が高く費用回収まで長い
家庭用蓄電池のデメリットとしてまずあげられるのが、高額な初期費用です。蓄電池本体の価格だけでなく、工事費用も加わると全体的なコストは約100万円になります。
また、蓄電池の電気代の削減効果で初期費用を回収するには時間もかかり、費用回収まで10年以上かかるケースも少なくありません。
そのため、多くの家庭では補助金制度を活用することで、初期費用を抑えて導入しています。
寿命による性能劣化がある
蓄電池は機器の性質上、寿命があり、充放電を繰り返すことで徐々に性能が劣化していきます。
リチウムイオン電池の寿命の場合は約10~15年とされていますが、使用状況や環境によって寿命は変動します。
なお、寿命が近づくと蓄電容量が減少し、十分な電力を供給できなくなる可能性があります。蓄電池の導入では定期的な蓄電池本体の交換も見越しておく必要があるでしょう。
設置場所の条件とスペースの確保
蓄電池を設置するには、一定のスペースが必要です。一般的な蓄電池のサイズは大型の空気清浄機程度であり、屋外または屋内に設置場所を確保しなければなりません。
特に屋外に設置する場合は、設置場所の環境条件にも考慮する必要があります。
高温や低温、直射日光や湿気の多い場所は性能や寿命に影響を与える可能性があるため、なるべく避けた方が良いです。そのため、マンションや狭小住宅では、適切な環境の確保が難しいケースもあります。
実際に使える電気量が少ない可能性
蓄電池は、充電した電力全てを使用できるわけではありません。
充放電の際にエネルギー損失が発生し、実際に使用できる電力量は蓄電容量より少なくなります。この充放電効率は製品と電池によって異なりますが、一般的には80~95%程度とされています。
また、日常的な電力使用量やピーク時の消費電力量に対して、蓄電池の容量が不足していると十分な電力供給ができず、期待した効果が得られない可能性があります。自宅の電力消費パターンを把握し、適切な容量の蓄電池を選ぶことが重要です。
家庭用蓄電池のデメリットを克服する方法

デメリットを理解したうえで、それらを克服するための蓄電池の選び方をご提案します。
家庭用蓄電池のメリットと比較する
デメリットだけに注目せず、メリットと比較することが大切です。
例えば、電気料金の節約効果や災害時の電力供給ができるなど、蓄電池には多くのメリットがあります。
ご自身のニーズやライフスタイルとも照らし合わせ、実際に蓄電池がもたらすメリットとデメリットを比較検討することが重要です。その上で投資に見合う効果が期待できるかを判断しましょう。
信頼性の高いメーカーと保証内容を確認
蓄電池は高額な製品であり、長期にわたって使用するものです。そのため、信頼性の高いメーカーの製品を選ぶことで、故障や性能劣化のリスクを低減できます。
メーカーの信頼性以外にも、メーカーや販売店が提供する保証内容やアフターサービスも重要な選択基準です。保証期間が長く、充実したサポートが受けられるメーカーの製品を選ぶことで、万が一トラブルが生じても安心できます。
適切な蓄電容量や種類を選ぶ
蓄電池にはさまざまな容量やタイプがあります。自宅の電力使用量や目的にあわせて、適切な容量を選ぶことが大切です。
一般的には、日常的な電力消費の70~80%をカバーできる容量が理想とされていますが、使用の用途によって必要な容量は左右されます。
例えば「非常用電源として使いたい」「EV充電にも使いたい」など、具体的にどのように活用したいのか決めてから容量を決めましょう。
また、蓄電池には「全負荷型」と「特定負荷型」があります。
全負荷型は家全体に電力を供給できるため、非常時にも全ての家電製品を使用できますが、その分価格が高めです。
一方、特定負荷型は、特定の部屋・家電にのみ電力を供給するタイプで必要最低限の電力供給に留まるため、全負荷型よりも費用は安く抑えられます。
蓄電池に使える補助金も活用する
国や自治体は、蓄電池の普及を促進するために補助金制度を設けています。これらの制度を活用することで、初期費用の負担の軽減が可能です。
ただし、補助金を活用するには蓄電池の製品や性能などに条件があるため、補助金の要件をしっかり確認することが大切です。
また、申し込みの締め切り日や上限件数も決まっているため、蓄電池を検討中の方は早めに準備しましょう。
国の補助金制度は、以下があげられます。
| 2024年までの補助金例 | 補助金額 |
| 子育てエコホーム支援事業 | 64,000円/戸 |
| DR補助金 | 1kWhにつき3.7万円(上限額60万円) |
ジャパンライフアシストでは、補助金の申請代行もおこなっているため、太陽光発電と蓄電池の導入を検討している方はお気軽にお問合せください!
※参考:エコ住宅設備の設置【リフォーム】|子育てエコホーム支援事業【公式】
※参考:令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
家庭用蓄電池を導入するメリット

ここでは、家庭用蓄電池のメリットについて詳しく解説します。
電気料金の節約が期待できる
蓄電池を導入することで、電気代の節約が期待できます。
具体的には、夜間の安い電力を蓄電池にためて昼間に使用する「ピークシフト」をおこなうことで、買電量を大幅に削減できる可能性があります。
また、太陽光発電と組みあわせて、昼間に電力をためて夜間に使用するという方法でも買電量の削減が期待できます。
この場合は昼間に電気をあまり使用しない方、または太陽光発電の容量が大きい方などにおすすめです。
停電時や災害時に電気が使える
近年、自然災害による大規模な停電が増えています。しかし蓄電池があれば、停電時にも一定の電力を確保でき、照明や冷蔵庫などの使用、スマートフォンの充電などがおこなえます。
また、太陽光発電と組み合わせれば、長期の停電時にも昼間に発電した電力を蓄電池にためて夜間に使用することが可能です。
このように蓄電池は災害時の備えとして、家族の安全と安心を守る重要な役割を果たすことができます。
環境へ配慮したエコな暮らしを実現できる
太陽光発電は製造や電力を生み出す過程でCO2排出量が少なく、再生可能エネルギーと呼ばれています。つまり蓄電池の導入をおこなうと、この再生可能エネルギーの使用量を増やすことが可能です。
結果的に環境へ配慮することにもつながるため、環境意識の高い方にとって蓄電池は特におすすめの選択肢といえます。
また、ピークシフトにより電力需要の平準化にも貢献するため、発電所の負荷軽減にも寄与します。
さらに、V2H(※1)システムも同時に導入すれば、電気自動車の充電にも使えるため、すでEV車を使用している方にもおすすめです。
※1)V2H(Vehicle to Home)とは、電気自動車と太陽光発電が取り付けられた家の双方向で電力をやり取りできるようになる機器。
家庭用蓄電池に関するよくある質問

蓄電池の導入を検討する中で、多くの方が抱える疑問や不安についてお答えします。
導入費用はどのくらい必要?
蓄電池の導入費用は、容量、機能、メーカーによって異なります。一般的には、本体価格と設置費用(工事費)をあわせて、約100万~200万円程度が目安です。
ただし蓄電池の補助金を活用することで、導入費用額を抑えることができます。具体的な金額は、販売店や工事業者に見積もりを依頼して確認しましょう。
メンテナンスはどうすればいい?
蓄電池の寿命は約10~15年とされていますが、使用状況や環境によって変動します。また、定期的な点検やメンテナンスをおこなっていれば、性能を維持し長持ちすることもあります。
メーカーや販売店による保証期間内であれば、故障や不具合にも無償で対応してもらえる場合があるため、購入時には保証内容をしっかり確認しておきましょう。
太陽光発電との連携は必須?
蓄電池と太陽光発電を連携させることは、必須ではありません。
しかし、蓄電池を太陽光発電と組み合わせることで、電気料金の節約や災害時の電力確保、自家消費の拡大などの多くのメリットが得られます。
まとめ

家庭用蓄電池を導入する際は、高額な初期費用、設置場所の制約などのデメリットは無視できません。
しかし、正しい知識を持ち、適切な製品を選ぶことで、電気料金の節約や災害時の備え、環境への貢献など多くのメリットを享受できます。
導入を検討する際は、自分の生活スタイルやニーズをしっかりと見極め、信頼できるメーカーや販売店と相談しながら進めていくことが大切です。
蓄電池の導入を検討している方は、ぜひジャパンライフアシストにご相談ください!まずは資料請求・お見積もりから!